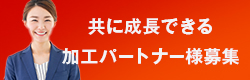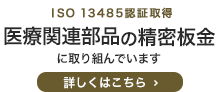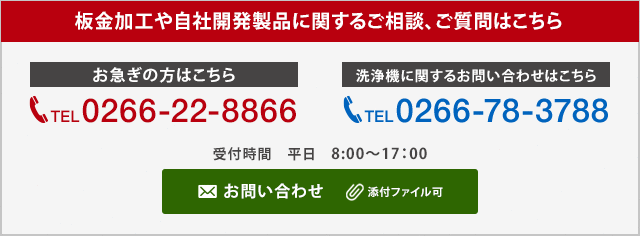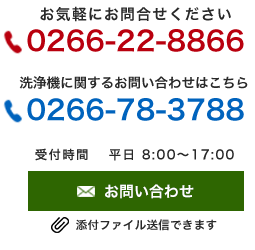ステンレス溶接の基礎知識と加工の難しさを徹底解説
ステンレス鋼は、耐食性や強度が求められる場面で広く使用される優れた素材です。
しかし、その特性ゆえに、溶接加工には特殊な技術と知識が必要です。
特に設計者や生産技術者にとって、ステンレス溶接の基礎知識を理解し、適切な加工方法を選定することが重要です。
本記事では、ステンレス溶接の難しさや加工方法、異種材との溶接時のポイントなどを詳しく解説します。
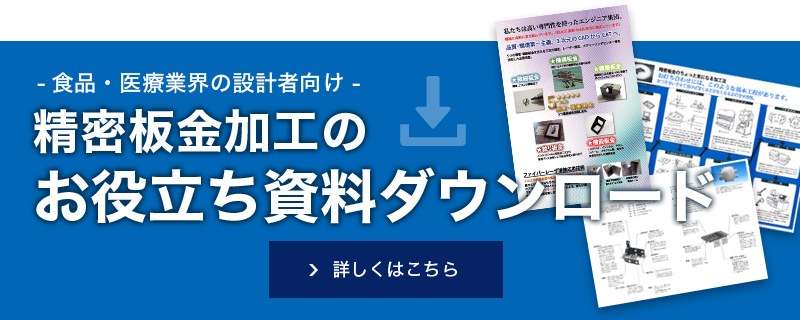
ステンレスの溶接加工とは?
溶接方法の概要とステンレス特有の特徴
ステンレス鋼は他の金属と比較して、耐食性が高く、見た目の美しさも持ち合わせています。
しかし、溶接時には金属組織が変化しやすいため、正しい溶接方法を選ぶ必要があります。
ステンレス溶接が難しい理由
種類ごとに特性が異なるため
ステンレスには複数の種類があり、それぞれ特性や溶接方法が異なります。
溶接時に適した方法を選ばなければ、品質が損なわれるリスクが高まります。
圧力に弱く割れるリスクがある
ステンレスは圧力が加わると割れることがあるため、溶接時には適切な圧力管理が重要です。
高温での歪みや割れのリスク
ステンレスは高温での歪みや割れが発生しやすく、冷却プロセスの管理が重要となります。
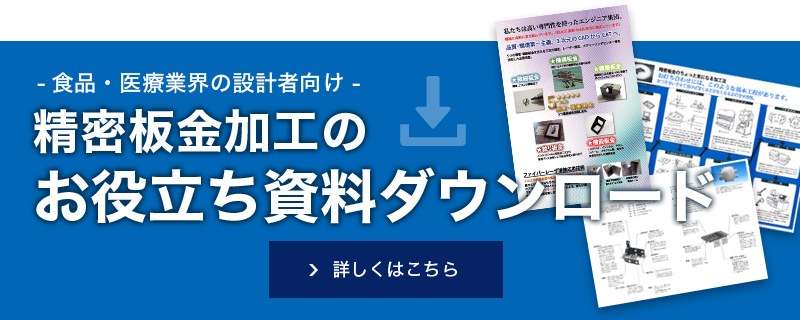
ステンレスの溶接方法6選
MIG溶接
半自動溶接機の一種。シールドガスに不活性ガスを用いますが、放電電極が溶ける溶接法です。
主に鋼の溶接に用います。
TIG溶接
アーク溶接の一種。TIGは、Tungsten Inert Gasの略で、電極棒にタングステンを使用して、電極を溶かさず、不活性ガスの中で溶接する方式です。
鋼、ステンレス、アルミが溶接でき、精密板金の中では最も一般的な溶接方法です。
被覆アーク溶接
被覆材を塗布した被覆アーク溶接棒を電極として、被覆アーク溶接棒と材料との間にアークを発生させ、その熱で溶接棒と母材を溶融させます。
被覆材の溶融によって発生するガスやスラグで溶融した材料を大気から保護して溶接することができます。
レーザ溶接
高エネルギー密度のレーザ光を熱源とした溶接方法です。
レーザ光の出力を調整することで、深さに対して幅の狭い溶込み溶接が可能で、入熱が少ないことから、低歪溶接ができます。
近年では、ファイバーレーザを用いた溶接が主流となっています。
スポット溶接(抵抗溶接)
電極で材料を挟んで加圧し、局所的に大電流を短時間通電させ、その際に生じる抵抗熱で溶接する方法です。
短時間で加工できるため、他の溶接方法と比べると安価である場合が多く、点で接合されるため打点数、ピッチなどから溶接強度を検討する必要があります。
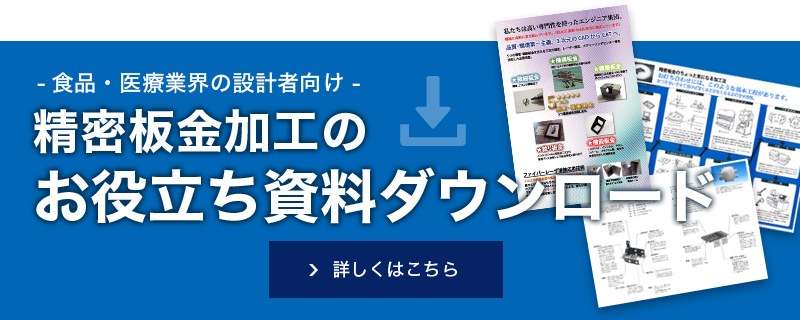
溶接に代わる接合方法の検討
必ずしも溶接が必要でない場合もある
溶接が困難な場合やコスト削減が求められる場合には、必ずしも溶接を選択する必要はありません。
接合という観点から、ステンレス同士を固定する他の方法を検討する価値があります。
接合方法の代替案
例えば、リベット接合やボルト接合は耐久性があり、溶接が難しい箇所での代替手段として有効です。
また、接着剤による接合も、比較的軽い部材であれば強度を保ちながら接合できる方法です。これらの方法は製品の用途や条件に応じて検討されるべきです。
数量や条件による溶接方法の選定
ステンレス溶接の方法は、製品の数量や形状によっても最適な選択が異なります。
大量生産の場合、コスト効率の良い方法を採用することで、コストダウンが可能になります。
また、部品の形状や溶接精度の要求度に応じて、MIG溶接やレーザ溶接など最適な方法を検討することが重要です。
ステンレスの種類とその溶接特性
ステンレスは精密板金でよく使われるアルミや亜鉛めっき処理鋼板などと比べて、溶接しやすい材料です。
SUS430
SUS430はフェライト系ステンレス鋼の一種であり、主に耐食性と磁性が必要な用途で使用されます。
ただし、溶接性に関しては特有の課題があります。
1. SUS430の溶接性の特長
| 熱影響部の脆化 | SUS430は炭素含有量が低いものの、溶接後の熱影響部(HAZ)で粒界に炭化物が析出することで、脆化や耐食性の低下が生じる可能性があります。 |
|---|---|
| 溶接後の結晶粒粗大化 | フェライト系の特性として、溶接熱の影響で結晶粒が粗大化し、機械的性質が低下することがあります。 |
| 溶接割れのリスク | SUS430は、溶接中や溶接後に「高温割れ」や「低温割れ」のリスクがあります。 |
2. SUS430の溶接性を改善する方法
| 溶接方法の選択 | TIG溶接(アルゴンシールドガス)やMAG溶接が一般的です。 熱の入力を最小限に抑えることで、熱影響部の脆化や結晶粒の粗大化を防ぐことができます。 |
|---|---|
| 低ヒートインプット | 可能な限り低い熱入力で溶接を行うことで、熱影響を抑えられます。 |
| 適切な溶接材料の使用 | SUS430の溶接には、フェライト系の特性を補うためにオーステナイト系の溶接材料(SUS304など)を使用することが推奨されます。 |
| 溶接後の処理 | 溶接後に熱処理を行うことで、粒界脆化を軽減し、機械的性質を改善することが可能です。 |
SUS430はコストパフォーマンスに優れていますが、溶接性を考慮する場合、プロセスの選定や後処理を慎重に行う必要があります。
異種材との溶接における注意点
異種金属の組み合わせによる溶接リスク
ステンレスと他の金属の溶接は、金属の特性が異なるため、接合部分の耐久性や腐食のリスクが高まります。
異種金属を溶接する際は、使用するガスや溶接方法の選定に注意が必要です。
溶接品質を保つためのポイント
専門的な知識と技術が必要とされるため、試作・評価のプロセスが重要です。
接合例・考え方
線溶接の代替案として、ブラインドリベットやスポット溶接があります。
ステンレス溶接の実績紹介

まとめ
ステンレス溶接は、その特性から高度な技術を要する作業です。
信頼できる業者の選定が品質に直結するため、ステンレス溶接の実績や専門知識を持つパートナーを選ぶことが重要です。
ステンレス溶接の難しい案件も、当社にお任せください。
豊富な実績と専門技術を活かし、精度の高い仕上がりをお約束いたします。ご質問やお見積もりのご依頼は、ぜひお気軽にお問い合わせください!